横浜の離婚弁護士トップ > 親権と子どもについて > 養育費 > 養育費の計算方法と具体例

いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。

離婚の相談ができる横浜の弁護士
〒231-0021 横浜市中区日本大通11番地
横浜情報文化センター11階
横浜綜合法律事務所
日本大通り駅 徒歩約0分(地下連絡口直結)
関内駅 徒歩約10分
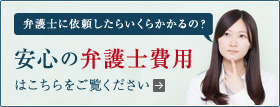
まず、収入の多い方の親の収入のうち、家族の生活費に充てることができる金額を求めます。これを基礎収入と言います。基礎収入は、各種統計等から、給与所得者の場合は総収入(源泉徴収票の支払金額)の34%〜42%、自営業者の場合は総収入(確定申告所の課税所得)の47%〜52%とされています(一般的に、総収入が高額であるほど、基礎収入の割合は小さくなります。)(給与所得者と自営業者との差については「養育費算定表で自営業者の金額が給与所得者より高い理由」も参照)。
この基礎収入額を親と子どもの生活費に割り振ります。この割合を生活費指数と言い、子どもが0歳から14歳の場合は、親が100に対して子どもが55、子どもが15歳から19歳までの場合は、親が100に対して子どもが90とするのが相当とされています。
その結果求められた子どもの生活費を、権利者(養育費を受け取る親)と義務者(養育費を支払う親)の基礎収入に応じて案分し、権利者が義務者に支払う金額が求められます。
この方法に基づいた計算の具体例については、下記の「養育費計算の具体例は?」を参照して下さい。また、養育費算定の基礎となる考え方については、「養育費算定表はどのような考え方で作られているの?」を参照して下さい。
例えば、8歳の子を監護する母親(権利者)の年収が100万円、父親(義務者)の年収が600万円の場合を想定します。
総収入に占める基礎収入の割合を、権利者は41%、義務者は37%と仮定すると(通常、収入が多い方が基礎収入の割合は下がる)、双方の基礎収入は下記の通りです。
次に、子どもの生活費は、義務者の基礎収入を、義務者と子どもの生活費指数で割り振って求めるので、222万円×55/(100+55)=787、742円となります。
これを、権利者と義務者の基礎収入で分配すると、787、742円×222万/(222万+41万)=664、938円となります。
これを12ヶ月で割れば、1ヶ月あたりの養育費は、55、412円となります(なお、これはあくまでも例に過ぎないことに注意して下さい)。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。

事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。

ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。
