横浜の離婚弁護士トップ > 離婚の諸手続きについて > 離婚が認められるケース > 離婚が認められる5つの理由

いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。

離婚の相談ができる横浜の弁護士
〒231-0021 横浜市中区日本大通11番地
横浜情報文化センター11階
横浜綜合法律事務所
日本大通り駅 徒歩約0分(地下連絡口直結)
関内駅 徒歩約10分
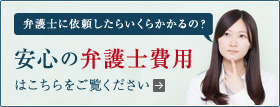
夫婦の協議で離婚が成立する場合や、調停で離婚が成立する場合は、あくまでも夫婦の話し合いで離婚する場合ですから、夫婦双方が離婚に合意しさえすれば、理由を問わず離婚が認められます。
これに対して、裁判離婚の場合は、特に法律で定める特別な理由が必要となります。裁判において夫婦の一方に法律で定められた原因(離婚原因)がなければ離婚は認められません。
民法は、裁判で離婚が認められる場合として、次の5つの離婚原因を定めています。
なお、裁判所は、①から④までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができるとされています。
不貞行為とは、配偶者がいるにもかかわらず、配偶者以外の者と肉体関係をもつことをいいます。夫婦にはそれぞれに一夫一婦制からくる貞操義務があるため、法はそれに違反した場合を離婚原因としているのです。
たとえば、配偶者が愛人と同居している場合はもちろん、同居はしていなくても、愛人と長く交際している場合は離婚が認められるでしょう。
また、不貞行為に愛情が伴っているかどうかは関係ないため、夫が売春婦を買った場合、妻が売春をした場合も、不貞行為となります。また、相手の合意があるかどうかも関係ないため、夫が女性をレイプした場合も、不貞行為となります。
なお、不貞行為により離婚が認められるためには、不貞行為により夫婦関係が破綻に至ることが必要なので、婚姻関係が既に破綻している状態で配偶者以外の者と肉体関係を持ったとしても、不貞行為として離婚の原因には該当しないと考えられています。
悪意の遺棄とは、正当な理由もなく、夫婦の義務である同居、協力、扶助義務に違反する行為をすることです。夫婦の一方が正当な理由もなく、配偶者や子を放置して、自宅を出て別居を続ける場合や、収入があるにもかかわらず、婚姻費用の分担をしない場合がこれにあたります。
別居について正当な理由がある場合としては、当事者双方が納得している場合(たとえば、子どもを進学校に入学させるため、妻と子どもが夫と一時的に別居するケースなど)のほか、当事者の一方が納得しなくても別居がやむを得ない場合(たとえば、仕事の関係での単身赴任、病気による長期入院など)があります。
3年以上の生死不明とは、離婚を求めて訴訟を提起する者が配偶者の生存を最後に確認できたときから、その配偶者が3年以上生死不明である場合のことをいいます。生死不明である理由はや原因は問題とされておらず、客観的に生死不明の状態であることが要求されます。いわゆる行方不明とは異なり、生きているか死んでいるかわらからない場合がこれにあたります。そのため、自宅を出たきりいっさい連絡をしてこないものの、知人には連絡をしているような場合はこれにあたりません。
また、「3年以上」は最後に音信があったときから起算します。
「強度の精神病」とは、夫婦の協力しあう義務を十分に果たすことができない程度の精神的な障害のことをいうと考えられています。また、精神病の「回復の見込み」の有無は病者が家庭に復帰した際に夫または妻としての責任を果たすことができるか否かによって決定されます。
もっとも、精神病者には療養看護が必要であり、かつ病者には責任がないので、たとえ強度の精神病にかかり回復の見込みがないとしても、簡単に離婚を認めてしまうとあまりに病者に酷な結果となります。
そこで、裁判所は、この離婚原因に該当する事情が認められるとしても、病者の今後の療養、生活等についてできる限り具体的方途を講じ、ある程度その方途が実現される見込みある場合でなければ、離婚を認めることは相当ではないとしています。
したがって、強度の精神病にかかったことを理由として離婚をしようとする場合には、それまで誠実に生活の面倒をみてきたこと、病者が今後も療養・生活できるように具体的な方策を講じたことが必要になると考えられます。
婚姻を継続し難い重大な事由とは、一般に、婚姻関係が破綻し回復の見込みがないことをいいます。その判断については、婚姻中における両当事者の行為や態度、婚姻継続の意思の有無、子の有無、子の状態、さらには双方の年齢、健康状態、性格、経歴、職業、資産収入など、当該婚姻関係にあらわれた一切の事情が考慮されると考えられています。
たとえば、婚姻開始当初から夫の強権的支配の下、妻が夫に服従を強いられ、妻は忍耐を重ねていた中でうつ病になり、その後、妻がカトリック教会に通うようになって自己主張を始めると、夫から肉体的暴力を受けるようになったことから、妻が子らとともに家を出て別居するに至った事案で、婚姻関係は修復困難なまでに破綻したと判断した裁判例があります。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。

事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。

ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。
